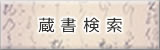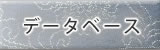古典芸能研究センターは、行吉学園発祥の地である三宮キャンパス(神戸市中央区)にあります。
能楽資料の橘文庫、民俗芸能資料の喜多文庫をはじめ、古典芸能や民俗芸能に関する書籍・資料を幅広く備えた研究施設です。芸能に関連する様々な分野の資料を収集しており、個別の分野はもちろん、より総合的な調査・研究の拠点となっています。
なお、所蔵する資料は、学生・社会人を問わずどなたにもご利用いただけます。
最新情報
- 2026年1-2月の開室日をアップしました。
- 2025年9月30日(火)~12月19日(金)、展示室において、令和7年展示「蔦重」と仲間たち―時代と文化のネットワーク―を開催してます。
- 2025年6月から 古典芸能研究センター公式チャンネルで、YouTube版「今月の資料」を公開します。
- 「古典芸能研究センター蔵 民俗芸能・民俗資料データベース」を公開しました。
最終更新日:2025年12月24日
今月の資料 (2025年12月)
古典芸能研究センター所蔵の様々な資料の中から、毎月1点紹介します。
YouTube版 2025年12月「今月の資料」はこちら
 『謳秘事哥袋』 (奥書と裏見返し) |
『謳秘事哥袋』 伊藤正義文庫蔵 袋綴写本1冊 縦14.8㎝×横10.5㎝の小型本 布目地型押浅葱鼠色表紙 全92丁 謡道歌を記した書物としては、現在知りうる限り最多の795首(重複1首)を144の謡習得上の項目に分類して収めている。項目名以外は、すべて和歌仕立てでそれぞれの修行の要諦を述べている点で、極めて特異な謡伝書と呼ぶことができる。室町後期以後の謡伝書に謡道歌が頻出することから、謡愛好家には和歌形式で謡の心得を記すことが好まれた結果であろう。作者、青地茂左衛門周盈(1745~1805)は、京観世の風を伝える謡指南の名家、小川庄右衛門の門流に連なり、謡は速水六郎兵衛円齋の門人、笛は森田流石井平三郎の門人、狂言は山脇和泉弟子であったことが知られ、素人ながら、謡・狂言・囃子事の秘事伝授を数多く受けている。 本書に示された項目からは、江戸期刊行の音曲伝書、とりわけ『音曲玉淵集』の内容を敷衍したものであることが確認できるが、各項目の冒頭に内容の大概を説明するような道歌が掲げられ、例示された謡本文が『音曲玉淵集』と相違することも多く、自身の稽古修行の実際に基づいて青地周盈が独自の見識で作成したものと認められる。同時に、『音曲玉淵集』が江戸後期の謡教授において教科書的な役割を担っていたことも、本書によって裏付けられよう。 本文末に添えられた三光院(三条西実枝)と桜町天皇の和歌は、それぞれ江戸時代後期には斯道執心と師訓敬愛の心構えを解く和歌として理解されていた。 ※本資料は、2021年9月に紹介した資料の再掲です。 |
当サイトのデータについて
神戸女子大学古典芸能研究センターが公開しているすべてのホームページおよびそこに含まれる画像データ・テキストデータ等は、神戸女子大学が著作権を有しており、その扱いは日本の著作権法に従うものとします。これらのデータを、法律で認められた範囲をこえて、著作権所有者に無断で複製・転載・転用することは禁止します。